
お勉強#6(メロの移調)・4/1008.05.28追加
#6,の前に全体を読み直してみて、判りにくいことを解説します。
移調譜を作るためには、まず自分の声域を知らねばならない、ということです。
移調する元の譜面を見て、自分の声域で歌えなかったら、何度(いくつ)下げたら、
何度(いくつ)あげたら唄えるか?を考えるのです。
仮に、貴方の声域がBb〜Aのほぼ2オクターブとしましょうか、
其の時元の楽譜の最も高いところがCだったとすると、高いところが出ませんね?!
何度下げればよいか、CをAにするには、鍵盤を見ればすぐわかりますが、
短三度、3つ、下げればよいとわかります。
でこれが大事ですが、元の楽譜のキーがCならAへ、DならBへ、EならDbへ、FならD、GならEへ、
と書き直すのです。上げるのも同じ要領。
音名なのか、コードなのか、キーなのか、わかりますよね?
最初にやったように階名で(ドレミファ)でメロディを読むのですから
移調したキーでも其のキーで読んだ階名通り書いていけばよいのです。
コードは元のコードから三つ下げたら何のコードになるかを考えて
コードシンボルだけを変更するのです。
お勉強#1で、A、B、C、D、E、F、G、は音名、と キー、を表すと書きましたが
実はもうひとつあって、和音、も表すのです。コードネームです。
このアルファベット(bや#が付いたものも)を、コードシンボル、といい、
その横に書く文字や、数字を、サフィックス
(付け加えるもの)といいます。
では実際に4小節ほど移調を、やってみましょうか。

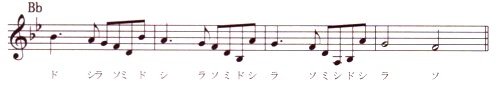
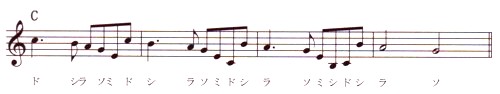


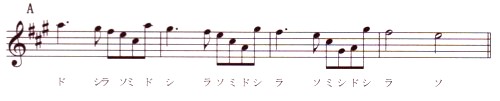
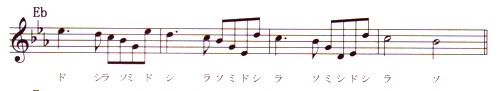
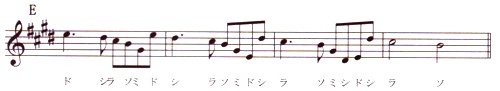
質問、待ってます。次はいよいよコード、ですよ。久富へのメールはこれをコピーしてお使い下さい。a.compi@nifty.com
次へ
トップへ
お勉強(明日のために)
仕事を通してお会いした方々 へ